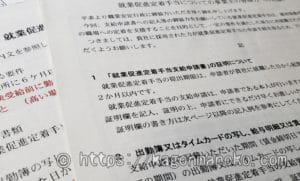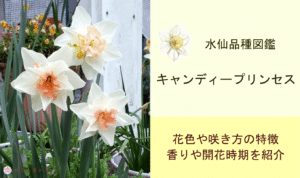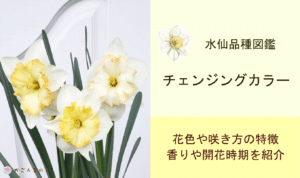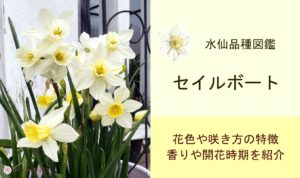落葉した紫陽花は樹形が分かりやすくなるため、剪定をして枝の数や向きを整える機会です。剪定した紫陽花の枝を活用して、もっと紫陽花を増やしたいと思ったことはありませんか。冬の挿し木は難しく、また冬に剪定をした紫陽花の枝は緑色の枝ではなく茶色く木質化してしまっていて葉もない枝だから、発根に失敗しそうと諦めて捨ててしまうことがほとんどです。今回、霜が降りる3月に木質化した枝(冬芽あり)で挿し木に成功したのでご紹介します。
目次
強剪定から取った挿し木
強い霜が降りる冬真っ最中の3月に鉢植えしていた紫陽花を地植えをしたのですが、地植えして数日経つと枯れそうになった紫陽花を剪定しました。その時に剪定した紫陽花の枝を挿し木にしたのですが、寒さに負けずに発根に成功しました。
3月に休眠中の枝を挿し木を準備する
冬の剪定のため、木質化した古枝で、葉もない紫陽花の挿し枝を2本準備しました。(写真1)今にも枯れそうな小さなわき芽は、茶色の木質の皮を被った状態でした。挿し木用の枝は若々しい緑色の太い枝を使った方が、水の吸収率もよく水循環が行われている枝の方が発根をしやすいといわれていますが、せっかくなので挿し木に挑戦してみます。
挿し木に使われる幹は今年伸びた緑色の枝です。木質化が進んでも、この厚い茶色の皮(木質化された皮)の下で緑色の元気な細胞は生きています。そこで試験的に右側の古枝だけ、外皮である木質部分をカッターで削ってみました。

右側)木質化を削った枝
左側) 通常の枝
fa-arrow-down fa-arrow-down fa-arrow-down fa-arrow-down

休眠挿しの枝を挿し木する条件を箇条書きにします。枯れる要因が揃っています。
fa-check-square-o葉はなく休眠中の枝
fa-check-square-o湿気もなく寒い時期(3月)
fa-check-square-o種まき用の土を使用
冬芽の挿し木が発根するまで
冬芽(休眠挿し)から葉がでた
挿し木を植えて1ヶ月した4月上旬に枯れかかっていたわき芽から新しい葉がでていました。
奥側)通常の枝
手前側)木質化を削った枝
fa-arrow-down fa-arrow-down fa-arrow-down

奥側)通常の枝を拡大します。
fa-arrow-down fa-arrow-down fa-arrow-down

挿し木をしてちょうど1ヶ月経った時点で、通常の枝(木質化したままの枝)の方がわき芽が芽吹いていました。木質した樹皮を削った枝は、通常の枝(木質化したままの枝)より生育が悪いでした。脇芽が少し小さかったことや木質を削ったことで枝のダメージが原因なのかこの時点で因果関係を追及できませんでした。分かったことは、水の吸収についてです。木質化した枝でも水を吸い上げる力があることが分かりました。
元気な葉が伸びた
挿し木をして1ヶ月と数日後の4月中旬は、遠くからでも見て分かるぐらいに葉が伸びてきました。
右上側) 通常の枝
左下側)木質化を削った枝
fa-arrow-down fa-arrow-down fa-arrow-down

さらに10日ほど経つと、通常の枝の紫陽花はだいぶ葉が増えてきました。一方で、木質化を削った枝も変化が見られ、わき芽から新しい葉が顔を少し出しています。
木質を削った枝も変化が見られたことより当初3月に挿し木をする際のわき芽の大きさや成長具合などその時の状態が、その後の脇芽を芽吹かせるまでに何かしらの影響を与えることが分かりました。また、木質を削っても、削らなくても挿し木の成功率には変わりないようです。
発根した
挿し木をして2カ月経った5月には遠くからでも見て分かるぐらいに葉が伸びてきました。
右側) 通常の枝
左側)木質化を削った枝
fa-arrow-down fa-arrow-down fa-arrow-down

一般的な挿し木時期である5~6月は2週間ぐらいで枝に変化があるのに対して、冬に挿し木をすると葉が芽吹き枝に大きな変化がみられるまで約2か月かかりました。冬の方が挿し木が成功するまでに時間が長くかかることが分かりました。
冬に発根する管理の仕方
発根に成功した管理は簡単で、基本的な挿し木の管理方法と同じだと思うのですが、念のためにまとめておきます。
減農薬で育てているので
虫さんに葉を食べられています
fa-arrow-down fa-arrow-down fa-arrow-down

②夜は玄関の中に入れた
③日中は屋根のある野外においた
⇒日中3~4時間ほど日光が当たるベランダで栽培
④北風が強い日や雨が降る日は玄関の中に入れた
※ルートンとメネデール液は今回、使用しなかった
※土は赤土だけではなくいろんな種類が入っている種まき用の土を使い、保水率をよくした
最後に
(休眠枝挿し)
冬は挿し木に成功するとは考えにくい状態でも、発根することが分かりました。今回は、休眠枝の挿し木で「休眠枝ざし」と呼ばれています。葉がない状態で冬芽だけあれば、木質した枝で発根ができます。霜が当たったり凍ったりしない場所(無加温の窓際やビニールハウス)で乾燥させないように管理することがコツです。
この記事が最後まで書けたのも紫陽花が発根してくれたおかげ(*^^*)今年はまだ開花しないと思うけど、来年は可愛いお花を見せてね。根してくれてありがとう。

おしまーい。