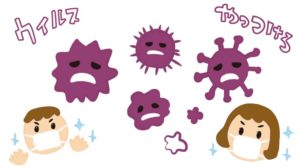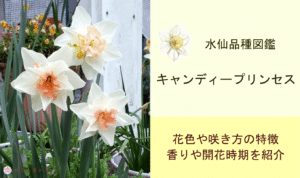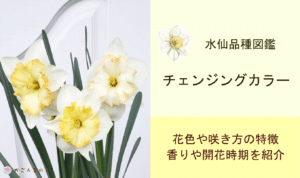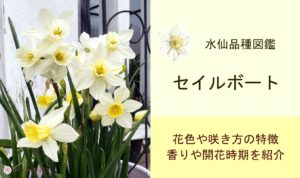この記事を訪れた方のほとんどは、我が子が同じ状況になってしまったか、もしくは今後気をつけておこうと事前に読まれる方だと思います。車の運転や乗り降りは当たり前の生活範囲なので保護者の不注意で目を離した時や油断した際に起こりやすい事例として気をつけて欲しいと思い記事にしました。
目次
ドアに指が挟まった理由
子どもの指がドアに挟まって、さらにドアが自動ロックされました我が家のお話をします。
その日は家族そろって夕食を食べ終わってから買い物に行った日で、事件は自宅の駐車場に着いた時に起きました。ママが荷物を車から玄関に運ぶために車のドアを少し半空きにしていたところ、パパと子どもが車から降りて、子どもが半空きのドアを開けようか閉めようかしている時に、駐車場の斜面の勾配上、ドアが自ずと閉まってしまいました。そのとき、車からセンサーが反応する距離に鍵がなかったため、自動センサーが働きロックがかかってしまいました。(鍵はママは持っていて、荷物の運搬のために玄関近くにいたため、車が鍵を持っている人が遠のいたからロックがかかったのでした。)
そして子どもが、ギャーーーー!と悲鳴をあげたと当時にパパが「鍵!指が挟まった」と叫んだんです。すぐに、ママは車に近づき、車のオートロックが解除されました。子どもは号泣。
指がドアに挟まってしまった原因を振り返りました。
暗闇での乗り降りで見えずらい環境だった
駐車場に勾配がありドアが閉まった
オートロック式で鍵が車が反応できる距離になかった
fa-arrow-down

パパとママがすべき判断
(救急車は必要?)
パパが「病院!病院!病院に電話」と焦り、ママは平日の夜にどこの病院に電話をしたら診てくれるのか分からず、さらに指が挟まったとなれば骨折やヒビ、打撲の可能性があるので「整形外科」の受診になりそうだけど、子どもの骨折を見てくれる病院が思いつきませんでした。正直、パニック状態です。
子どもはパパに抱っこされたまま「痛いよー」と泣き叫び、指が変形している状態でした。そこで、消防本部の救急隊に連絡をして事情を説明して「受診できる病院を教えて欲しい」と伝えたら「119番してください。」と説明され、すぐに119番すると救急車が自宅に到着しました。
振り返るとこのような状態だった時、パパとママがすべき判断は次の4つのことだと思います。
落ち着いて、状況判断
まずは、落ち着くことです。車のどこにどんな状態で挟まったかを把握し、挟まった指の症状を確認します。今回は、ドアロックがかかってしまったわけですが、ドアロックが作動したということは一体、どんな状態だとロックがかかるのか振り返ると完全にドアが閉まっていて、ロックをかけられる車の状態ということです。つまり、半ドアでもなく、ドアと車に隙間があったわけではないということです。この点を踏まえて、ドアの隙間(ドアと車の隙間ではない場所)に指が挟まって押し付けられている状態であると考えられます。しかし、あくまで推測です。子どもの指は細く小さいのでドアの閉まる圧に負けてしまい、骨折や骨にヒビが入った状態かもしれません。
挟まった指の経過を診る
挟まった指を見ると、ドアに挟まった圧で身がくぼんでみえて外観は指が変形しているように見えることもあります。安静にした状態で負傷の程度を把握します。
指が曲がるかどうか
指のどこが痛いか
指が腫れているか
指に出血があるかどうか
fa-arrow-down

指しゃぶりの写真を掲載したので、子どもの指しゃぶりを辞めさせたいと思っている方に参考記事をご紹介します。
子どもの泣き方がどうなのか判断する
子どもは痛くて泣きますので、どのくらい泣いているのかいつもの泣き方とどう違うのかを分析していきます。子どもの性格にもよりますが、途中で子どもが泣き止むこともあります。
受診まで冷やしておく
負傷した指を早く冷やす必要があります。病院に連れて行くか行かないかの課題の前に、冷やします。氷袋を直接当てるのではなく、氷をお水を入れた袋を用意し、タオルを巻いて患部に当てて冷やしてあげます。
問診内容・症状が治るまで
挟まった直後の診察
整形外科ではまずレントゲンを撮りました。レントゲンを撮るときには我が子は泣き止んでいました。優しい看護師さんだったこともあり、子どもと看護師さんの二人でレントゲン室に入り、手を広げた様子とコンコン(狐さんのポーズ)をした様子の2枚のレントゲンを撮りました。その後、先生の診察がありました。
レントゲンの様子


fa-arrow-down fa-arrow-downfa-arrow-down

指が曲がるようになった
3日間ほど自宅で過ごした後、湿布を貼って保育園に登園することになりました。


挟まってから2週間後の診察
車に指が挟まった事故当日から2週間後にもう一度経過観察のため病院を受診しました。
経過2週間後のレントゲン
fa-arrow-downfa-arrow-downfa-arrow-down

2週間後の診察では「骨に異常はありません。」とのことで最後に受診となりました。
車の乗り降りでの対策
前頭にも書きましたが、fa-asterisk最大の要因は親の不注意と一瞬の油断です。
車の乗り降りの時に気を付けるとことを箇条書きで載せます。
2. 抱っこが難しい場合は、手をつないで明るい場所まで一緒に行く
3. 車のドアが自動的にしまらないように、駐車場の勾配に気をつける
(もう少しシビアに気を付けるとしたら)
5. 夜に子どもを連れて外出をできる限り控える
最後に伝えたいこと
子どもが傍に居るときは、目を離さず安全を確認しながら行動しても怪我をすることがあります。そんなときは、保護者は冷静に落ち着き、怪我の原因や症状、子どもの様子をしっかり確認し、適切な処置をしましょう。
一番は子どもが怪我をしないように最善の注意をしなければなりませんが、どうしてもそれが叶わなかったときもあります。そんな時、ママやパパ達は子どもに「ママ達がちょっと目を離してしまったから痛い思いをさせてしまってごめんね。病院に行こうね。」と謝って、子どもが安心できる言葉をかけてあげましょう。それが子どもにとって一番の治療ですから。
おしまーい。